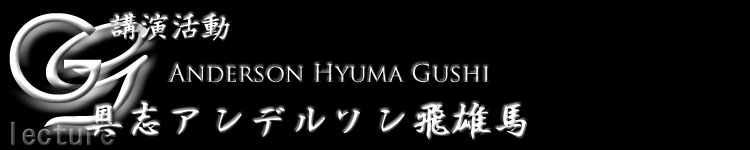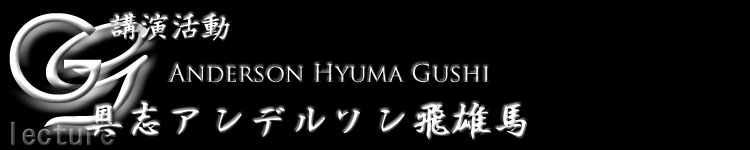三重県かたつむりの会 (2003年12月4日)
|

かたつむりの会
当日、会場の入り口に貼っ
てありました。
辻先生直筆です。
今でも大事に僕の
部屋にしまってあります。
|
かたつむりの会を紹介します。
「かたつむりの会」は三重県紀勢町にあり、5年前に発足。保護者と共に同和教育を学ぶ場を作っていこうということで、当時の同推教員が始めたものです。学校で子どもたちに正しいことを教えても、家庭で間違ったことを伝えては逆効果であり、より深い差別心が子どもたちに育っていくことになると考えたそうです。目的は部落差別を解消していくことです。 |
自分のコメント
この日はデジカメもビデオカメラも持っていきませんでしたので、皆さんにお見せするものがありません。とても残念です。
本当に素晴らしい会でした。普段から呼ばれる場所のほとんどが、在日世界人の生徒がいるので、在日世界人問題について学習したいという学校教員の依頼がほとんどでした。
ところが、この会から依頼された時、本当に驚きました。在日世界人の子どもは一人もいないと言うのです。それに、参加するのは子どもと教員と保護者で約100人くらい。
そして、講演当日には70%以上の保護者が出席していたということが、あとからわかりました。皆さんの熱心な人権啓発活動に関心すると共に心より感謝します。
当日は広くてとても綺麗な会場でした。なにより、真剣に話を聞く皆さんの視線が僕を圧倒して、思わず緊張してしまいました。
また、この依頼がきっかけとなり、僕は教員以外の方々にも聞いてもらえるような講演にしていこうと決意しました。その後、工夫を重ね今ではおかげさまで、教育現場以外からも様々な依頼が来るようになりました。
その後、「かたつむりの会」のつながりからいくつかの依頼が届きました。どの現場も一人ひとりがあつく出迎えてくれました。皆さんとの出会いは本当に素晴らしかったし、これからも皆さんとの出会いを決して忘れることはありません。本当にありがとうございました。 |

会場の壁に貼ってあった
ものです。
辻先生直筆です。
あんまりにも綺麗だった
ので、後日、辻先生に
お願いをして、
送ってもらいました。
|
依頼の経緯
正しいことを知ることは、自分の幸せにつながる。偏見をもった生き方は、人も傷つけ自分も不幸にしていくことに気づいてほしい。その中で、この人にお願いしたいと全員が強く思ったのが「具志アンデルソン飛雄馬」さんである。世界人差別についての学習となると、紀勢町では、世界の方に出会うことが少ないので、遠い差別を学習することになってしまうのではないかという心配もあった。しかし、自分達も子ども達も、少しこの町を出ると世界の人達に会う。松阪の高校に行った子どもが、同じクラスにいる世界の子どものことを話す。町で見かける人達のことを話す。話の内容に差別的なことが入っていて、その考えはおかしいと言えても、何故なのか、世界の方のことを知らない私達は、なかなか答えられない。日常生活の中で、なかなか話すことが無い人達・・・でも、自分たちが見かける人達が、日本でどんなことに戸惑いどんなふうに考えているのかを知ることが必要なのではないか・・・。また、どんな差別も根は同じなのかもしれない。具志さんにお願いしてみようということになった。 |