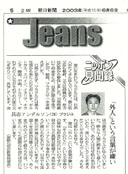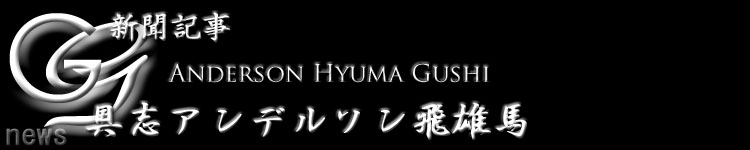
新聞記事
|
||
| 生きる希望 必ずある いじめ体験を語り続ける 底冷えのする体育館で、200人余りの中学生がひざを抱え、静まりかえっていた。 昨年12月中旬、冷たい小雨が降る三重県名張市の中学校。ワイシャツ1枚で話しかけた。 「これが、5年前の僕です」。スクリーンには、忘れたいはずの「過去」が映し出されていた。バイクの集団を引き連れた自分。改造車の前でカメラをにらみつける自分。「なんで非行に走り、なんで更生できたんか。それを、みんなに伝えていきたいと思います」 10代の半ばから、けんかと暴走に明け暮れた。暴走族のトップに上り詰め、18歳で引退すると、今度は車を連ねて夜の街を走り回った。最初の逮捕は19歳の時。2度目に逮捕された後、妻と離婚した。 生まれは、ブラジルのサンパウロ。日系3世だ。2世の父が日本に職を求め、一家5人で津市に移住したのは、11歳の冬。小学校で待っていたのは、外国人差別といじめだった。「ガイジン、気持ち悪い」。辞書でその意味を知り、周囲がどう見ているのかを知る。無視され、やがて暴力へと変わった。 中学に入ると、いじめは激しさを増したが、教師は見て見ぬふり。中学2年の夏、「けんかだけはしちゃダメ」という母との約束を破った。それからは、めちゃくちゃに暴れた。「誰も理解してくれず、守ってもくれない」のが理由だった。 中学を卒業しても、定職には就けなかった。「死ぬしかない」と思い詰め、ビルの屋上に上ったこともある。そんなころ、手を差し伸べてくれたのが、5年前に死んだ父が引き合わせてくれた知人の自然食品販売会社社長だった。 何も聞かず、説教もせず、仕事先に連れていってくれた。教えられたのは、世の中の広さだ。自分も変われると思った。 ただ、一度染まった世界を抜け出すのは、並大抵のことではない。「生き方を変えることを、古い仲間はどう思うか。逮捕歴のある外国人を一般社会は受け止めてくれるのか。でも、いつか抜けたい」。まずは恩人の社長のもとで、営業の仕事を覚えることから始めた。 周囲を説得し、過去の自分と決別できた時、23歳になっていた。 自らの体験を語るようになったのは、母校の教師に頼まれたのがきっかけだ。子どもたちの前で、身の上話を1時間余り。話が終わると、その教師は、「自分には教壇に立つ資格がない」と言って泣き崩れた。 口コミで講演依頼は増え、役に立つのならと引き受けるようになった。 講演は300回を超えた。いつも真剣勝負だ。当日は、朝から何ものどを通らない。すさんだ生活がよみがえり、夜は決まって悪夢にうなされた。「過去を美化するのか」という苦情が寄せられたこともある。 それでも、理解してくれる人や、生きる希望を見つけてくれる子どもたちが一人でも増えれば、それでいい。やっと居場所が見つかったと感じている。 最近は、「頑張れ」と励ましてくれる人も増えてきた。講演の後、子どもたちが握手を求めてくるのが何よりうれしい。 もう道を見失うことはないだろう。「死んだら終わり だから生きるんだ」。講演タイトルは、自らに向けたメッセージでもある。(梅村雅祐) (おわり) 「前妻との子ども2人は、長女が7歳、長男が6歳。実家で母親の手を借りながらだけど、シングルパパとして子育ても奮闘中です」 移民と日系人 日本人の最初の移住は明治元年のハワイ。以後、カナダ、豪州などが続き、戦前77万6000人が北米、南米などに移住した。こうした移民の子孫が日系人だ。 最初のブラジル移民は、1908年6月18日、移民船「笠戸丸」で海を渡った781人。多くはコーヒー農園で働いた。現在の日本からブラジルへの移民は1世から6世まで140万人を数える。 90年6月、出入国管理及び難民認定法が改正され、日系2,3世には就労も可能な「定住者」ビザ(最長3年)が与えられることになった。猛烈なインフレに苦しんでいたブラジルから大量の日系人が入国。ポルトガル語しか話せない子どもを受け入れることになった学校現場で混乱するなど、大きな社会問題となった。 今年は、ブラジル移民100周年にあたる。 |
|
||
| いじめの傷語って300回 犯した過ち批判覚悟 小学生の頃からいじめを受け、非行に走った経験をもつ日系ブラジル人の具志アンデルソン飛雄馬さん(28)が、三重県の小中高校で外国人児童の日本語指導にあたっている。外国人へのいじめや差別をなくしたいと2002年から始めた講演は300回を超えた。具志さんは「差別がいかに多くの人を傷つけるか知ってほしい」と話している。(原田朱美) 具志さんが家族と共にブラジルから津市に移住したのは、11歳の時。日本語を全く話せない外国人に同級生は冷たかった。「手でご飯食べてるだろ」。突き飛ばされ、けられた。言葉や習慣を知らないだけなのに笑われた。 いじめは年々激しくなった。でも、やり返さなかった。「ここは自分の国じゃない。好きにしてはいけない」と、両親から止められていた。 中1のある日、ついに相手の生徒を殴り返した。なぜやったと問いつめる教師には、こたえなかった。「悪いけど、日本人は信用できん」。来日して約2年。味方はいないと、心を閉ざした。 暴力をふるうことで、初めて自由になった気がした。高校を中退、暴走族に入った。ケンカをするために街を歩き、自分より強そうな者を殴って英雄気分に浸った。 しかし、いくら拳をふるっても、幸せは得られなかった。「このままだとただのクズ」。知人の言葉にショックを受けた。息子の非行を嘆いていた父は2001年、「何もいいことがなかった」といい残し、くも膜下出血で亡くなった。 父の死をきっかけに生き方を変えようと勉強を始めた。2002年、津市と松阪市の小中学校を巡回する国際化対応教育指導員になった。かつての自分のような子どもたちを助けたかった。 学校などで講演も始めた。依頼は全国に及ぶ。自分が犯した罪を語ることは怖かったが、訴えたい気持ちが勝った。 すべての人が理解をしてくれるわけではない。非行を美化したいのかと何度も言われた。自分の過去を非難されるのは、構わない。ただ、そうやって非行に走る子どもたちの背景は、知ってほしい。 今春、一つの事件があった。具志さんが教えるパブロ君(13)が、障害のある女の子をいじめていた同級生を「やめろ!」と怒鳴りつけたのだ。いじめは、ぴたりとやんだ。自分も嫌な思いをしたから、他人に同じ思いをさせたくないと、パブロ君は言う。「逆に自分がやられるかもと怖かった。でも、具志さんと会って成長したから」。 具志さんは今年1月、「多文化共生NPO世界人」を立ち上げた。外国人児童の生活相談や交流会などを開く。いつか、日本で育った彼らと共に、差別のない社会を目指して活動したい。それが、具志さんの夢だ。 |
|
||
| 「死んだら終わり、だから生きる」 少年時代の心の傷を語る 「死んだら終わり、だから生きるんだ」ー。外国人の子どもを支援する「多文化共生NPO世界人」理事長で、ブラジル出身の日系三世・具志アンデルソン飛雄馬さん(28)=津市=が、こんなタイトルの講演会を愛知県小牧市で開いた。具志さんは少年時代、学校や地域に居場所がなく非行に走り、大人になってからも「暴力」から抜けれない生活が続いたという。今、再び前向きに生きようと決意し、自分の生い立ちを語ることで「これからの子どもたちに、同じような過ちを繰り返させたくない」と訴える。 (酒井ゆり) 具志さんは十一歳の時、サンパウロから家族とともに来日。地元の小学校に通い始めたが、しばらくすると同級生たちの輪に入れてもらえなくなった。「外国人のくせに」「くさい」などと笑われたこともたびたび。「先生の目が届かないトイレや休み時間中は、殴られたり、けられたりが日常茶飯事だった」 中学校に入ると、いじめはさらにエスカレートした。「ご飯は手で食べているんだろ」「おまえの日本語、気持ち悪い」。度重なる暴言に耐えきれず。一度相手を殴ってしまったことがあった。そこだけを見た先生は「おまえが悪い。謝れ」と言った。「この時、自分はここに存在している意味はないとさえ思った」。 それでも高校への夢は捨てきれず、定時制に進学。そこでも暴力が待っていたが、今度は殴り返した。すると、不思議と仲間が増えていった。「不良は、自分たちも心に傷を抱えている。だから、以前のように外国人だからと言うだけで、差別されることがなかった」けんかしている時だけは、生きている充実感が味わえた。 その後、仲間うちで傷害事件が発生。逮捕され、約一か月後に釈放されたが、その後も生活は変わらなかった。「内心はまじめになりたいと思った。でも、なかなか仲間と縁を切ることができなかった」。 転機が訪れたのは二十歳の時。子どもが生まれ、真剣に生活を考えていかなければならなくなった。父親の知り合いの社長が営業の仕事を紹介してくれた。頑張れば、頑張るほど、売り上げが伸び、働くことの楽しさを知った。 ようやく前向きに頑張ろうと思ったころ、父親が病気で他界。最期は「四十八年間生きてきて、何も楽しいことがなかった」とだけ言い残して。「あまりにも悲しい言葉。また生きる気力がなくなった」。荒れた生活に戻り、再び傷害事件を起こして塀の中へ。だが、そこで出会った年上の人に「あんたみたいな若者が、こんなところにいたらあかん」とさとされて、思った「99%だめな人間でも、1%でも価値があれば生きていけるのだと」。 社会に復帰した後は、それまでの仲間とはきっぱり決別。今は三重県内の学校で国際化対応教育指導員として、外国人の子どもたちのサポートに尽力している。今回の講演は少年支援のNPOジュヴェニルの活動に協力した。「今でも僕と同じような状況の子どもたちがたくさんいる。自分の生い立ちを話すことは苦しいが、こうした子どもたちの気持ちを少しでも分かってもらいたい」と言う。 支援活動の傍ら、大学進学を目指して受験勉強にも励んでいる。外国人の子どもたちが、少しでも将来に希望が持てるようにー。 |
|
||
| 「外国人受け入れ整備を」 経験交えて講演 東淀川一丁目の市立日之出人権文化センターはこのほど、多文化共生社会の在り方について考える講演会を同館で開いた。講師を務めた日系ブラジル人三世・具志アンデルソン飛雄馬さん(26)=三重県=が自らの人生を振り返り、真の国際化が求められる日本での外国人の受け入れ態勢を整えることの重要性を説いた。 具志さんは、三重県内の小中高校で国際化対応教育指導員として、外国人児童生徒らをサポートする一方、各地で講演活動などを行っている。 講演会で具志さんは、ブラジルに移住した日本人の子孫である日系ブラジル人の歴史背景を説明する一方、十五年前にブラジルから来日し文化や言葉などの違いに悩まされ、学校や社会で受けた差別から非行に走った経験を語った。 「ジャパニーズなのに」差別を受けることで直面したルーツへの戸惑い、非行グループの長となりその世界から抜け出せないあせり、父の死で自責の念に駆られ自暴自棄になったことなど、心の葛藤を赤裸裸に告白。「死なずに生きてきて良かった」と含蓄ある言葉で振り返る具志さんの人生を垣間見て、来場者ら約五十人は目頭を押さえていた。 また、国内には約百八十万人の外国人が在住し、その数は増加傾向にあるものの教育現場での外国人の受け入れ態勢は整っておらず、子どもが抱える人権問題は当時と変わっていないことを強調。 「国際化が進むことで日本での差別の歴史は変わると思う。日本の国際化社会に貢献していきたい」と熱意を見せた。 (寺田英祥記者) |
|
||
| 講演先で感じること 学校の先生や子どもたち、自治体職員などを前に、講演する機会がよくあります。そんな時、僕自身が日本の学校で受けた外国人差別の体験を話すことにしています。残念ながら、差別は今もなくなっていませんし、自分の過去を人前で話すのはとてもつらいことですが、何かが変わることを信じて続けています。 地元の三重県だけでなく、大阪府や、奈良、和歌山、岐阜、愛知の各県にも行きました。各地を回ることで、いろいろな情報を得ることができますし、1人でも多くの人に、僕の体験を聞いてほしいからです。最初から最後まで熱い視線でずっと聞いてくれる人、自分のことのように共感して涙を流してくれる人。壇上からそういう姿を見つけると、胸が熱くなります。幼いころからいじめられていたという高校生が「苦しかった思い出に立ち向かっている具志さんを見て、おれもがんばれそうな気がしてきた」と感想を寄せてくれたこともありました。 講演先での反応から、知らず知らずのうちに差別をしてしまう人もいることがわかってきました。現状を少しでも変えるため、どこへでも出かけて、一度でも多く語っていきます。 (国際化対応教育指導員) |
|
||
| 「外人」という言葉が嫌い 僕の生まれたブラジルには、日系人がたくさん住んでいます。僕の祖父母も戦前、父方は沖縄から、母方は広島から移住しました。10年間働いてお金をため、日本に戻る予定でしたが、結局、ブラジルで一生を終えました。 日系に限らず、ブラジルには様々な国から来た人たちがいます。ポルトガル、スペイン、イタリア、オランダ、韓国、中国、トルコ・・・。それぞれの人たちがそれぞれの国の文化を守りつつ、共存しています。僕は10歳までブラジルに住んでいました。様々な人種に囲まれて暮らしていたので、あの人はなぜ肌の色が白いのか、黒いのかということを考えたことがありませんでした。今もそれは変わりません。 僕は「外人」という言葉が嫌いです。「そとのひと」という文字通りの意味も好きになれないのですが、自分たちと異質な敬遠すべき存在といったニュアンスが含まれているように感じられるのです。日本でも国際化が声高に叫ばれていますが、外国人を日常的な隣人ではなく、あくまで外の人として扱ううちは、いつまでたっても国際化社会にはなれないと思います。 (国際化対応教育指導員) |
|
||
| 日本語が必要な子らのために 日本には様々な国の人が生活していますが、誰もが日本語を話せるわけではありません。日本語ができず、困ったり差別されたりしている人は多いでしょう。日本語しかできないあなたが、ブラジルに行ったときのことを想像してください。不安なく生活できますか。 日系3世の僕は10歳のときに来日しました。日本語は全くできませんでした。今、自分の経験をもとに、三重県内の小中学校を回り、日本語を必要とする子どもの指導をしています。言葉ができず、いじめられた経験を日本の生徒に話すこともあります。ある生徒は「僕は外国人を避けていた。僕らとは違う存在のように思っていたが、同じなんだ。これからいつ外国籍の子が転校してくるかもしれない。言葉が違うだけで、中身はみんな同じ人間だ。もう差別はしません。自分もされたらいやだから」という感想を寄せました。感想文は何十人分もありましたが、10人分しか読めませんでした。涙が止まらなかったのです。 来日15年目になります。日本人が信用できず、いやなことがほとんどでした。でも少しでしたが素晴らしい感動もありました。今は、日本を心の底から愛しています。国際理解が深まるように、また日本語を必要とする子どもに明るい未来を与えられるようにと思い、活動しています。 (国際化対応教育指導員) |
|
||
| 日本語話せず、帰りたかった 僕は78年にブラジルのサンパウロで生まれた日系3世です。父が日本に働きに行って8カ月後、「日本はいい国だよ。皆も来なさい」と電話がありました。13年前のこと、家族全員で来日しました。 正直、不安でいっぱいでした。どんな国なんだろう?日本人は、皆金持ちで空手がすごく強いイメージでした。日本に着いたのは89年2月15日午後1時30分。今でもはっきり覚えています。 日本での生活は、本当に苦労しました。言葉が話せない、食べ物も違う、友達もいない、本当にこんな国で生活していけるのかと思いました。 そう考えているうちに僕もある工場でお手伝いをすることになりました。10歳でした。間もなく津市内の小学校に行くことになりました。日本語は何も話せません。ただ、母から「返事をする時、ハイと言うように」と注意されていました。 友達からよく殴られたこともあります。僕はある日、母に言いました。「ブラジルに帰りたい、1日でも早く帰りたい」。ブラジルに帰れば本当の友達が僕を待っていると思いました。 きっと異国でこんな悩みを抱えている外国人の子どもたちも多いはずです。今、僕は、自分の経験を振り返り、津や松阪市で彼らの教育相談員として働いています。 (外国人児童生徒教育相談員) |