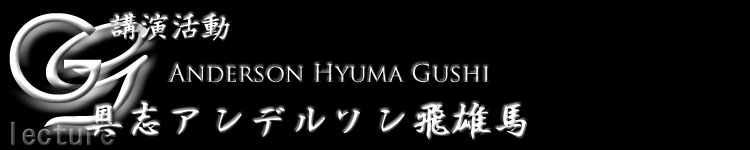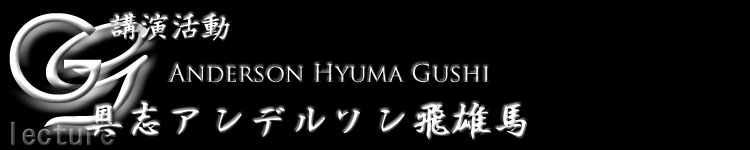�鍑�x�z�ƕ�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�{�@���l
�P�@�͂��߂�
�@�P�X�U�T�N�ɓ��t������b�֒�o���ꂽ�u���a���R�c��\�v�i�u���ΐR���\�v�j�i�P�j�́A�u���a���́A���{�����A���{�����̂Ȃ��̐g���I���ʂ������鏭���W�c�̖��ł���v�ƋL���A�������ʂ�������ł���A���{�ŗL�̖��ł���Ƃ����B���̓��ΐR���\�̔F���́A������������̎咣�̑������̂肢���ꂽ�Ƃ������Ƃ������āA���̌�̐l���s���E�l������̒��Ŋ�{�I�ȔF���Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ�B�����āu�����j�v�����ɂ����Ă��A�]������́u�����j�v�̂Ȃ��́u�ʎj�v�Ƃ����g�g�݂̌Œ艻������ɂ͂����Ă����傫�ȗv���̈�Ƃ��Ȃ����B
�@����ɑ��ĂP�X�X�O�N�ɂЂ낽�܂������́A�������ʂƑ��̍��ʂƂ̋��ʐ���A�u�ߑ�v��u�������Ɓv�ƍ��ʂ̑n�o�Ƃ̊֘A�����𖾂��錤���̕K�v�����N�����m�Ђ낽�P�X�X�O�n�B������āA����݂ǂ莁�́A�l���`(racism)�̐F�Ȃǂɂ��ƂÂ��u�l��v�����łȂ��A�u�����I���فv���܂߂����̂Ƃ��ĂƂ炦�A�������ʂ�l���`�Ƃ��Ĉʒu�Â��鎎�݂��s�����m����Q�O�O�T�n�B�l����Ɋւ��āA���䒼�����́u�����Ɍ��o�����l����́A���O�ɂ��鍑�ۓI�Ȓ����Ɛ藣���ė������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�A�u���O�͍����ɌJ�肱�܂�Ă���v�Ƃ����d�v�Ȏw�E���s���Ă��邪�i����Q�O�O�W�j�A�������ʖ��Ɋւ��Ă������������������߂��Ă��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����낤�B���������āA�{�e�ł́A�Ђ낽�A���쎁�ɑ�\����錤���̗�����ӂ܂��A���ۓI�Ȓ����␢�E�I�ȘA���Ƃ̊֘A����A�������ʖ��̐����ƑS�������Ђ̑n���̈Ӗ��Ɋւ��Ă̖���N���s�������i�Q�j�
�@�Ȃ��A���̃��|�[�g�́A�{���K�v�Ƃ����j���̏\�S�Ȏ��؍�Ƃ̑������Ȃ�������߂ĊȌ��Ȃ��̂ł���B
�Q�@���ۓI�Ȓ����Ƃ��Ă̐l���`�E�A���n��`
�@���{�����E�V�X�e���ɎQ�����ꂽ�P�X���I�㔼�A�����͖{���̎��{�̓�����A�����ȘJ���͂�G�l���M�[���̋����您��э����̎Љ���̂͂����̊m�ۂȂǂŔ[���b�p���E�̑��D����J��Ԃ��Ă����B�����ł͌��O�ł���Ƃ͂��������匠�Ɛl�����d�̌������K�p�����{���ƁA���ʂƖ\�͂ɂ��炳��A���ۖ@�̕ی삪���҂ł��Ȃ��A���n�Ƃ����A���ꂩ�疵��������̌������������Ă����m����Q�O�O�W�A�|��Q�O�O�T�n�B�u�l�핽���v�Ƃ������Վ�`�I�ȗ��O���炷��ƁA�{���Ȃ�A���n�ɑ��Ă��l�����d�Ƃ������Ƃ�K�p����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��͂��ł������B�������A�A���n�̌����͂����������ՓI�ȗ��O�ɑ��闠����ؖ����Ă���A���̂��߂ɐA���n�x�z�𐳓������鍪�������߂�ꂽ�B�����œ������ꂽ�̂������ł��肾���ꂽ���܂��܂ȏ��Ȋw�ł���A�Ȃ��ł��A�]�̗e�ʂ��͂���A���̏������������ɍ��l��L�F�l��̗����u�Ȋw�I�v�ɏؖ����悤�Ƃ����|�[���E�u���J�Ɏn�܂�t�����X�́u�l��_�I�l�ފw�v�́A�ߑ�l���`�̐����Ɍ���I�Ȗ������ʂ������m�n�ӂP�X�X�V�A�|��Q�O�O�T�n�B
�@���̂悤�ȐA���n�ɂ������l���I�ȍ��ʁE�}���̍����ƂȂ����l���`�́A��p�鍑�̐A���n�C���h�Ŕ������ꂽ�w��@����A�t���J���o�Ė{���ł̐l�Ԃ̊Ǘ��E�����̋Z�@�Ƃ��Đ�������Ă������悤�Ɂm�n�ӂP�X�X�U�n�A�������ƍĕ҂ƍ����`���ɂ͂���ł����{���t�����X�ւƊҗ�����Ă������B�A���n�����ɗ��l���`�ɂ��u�N���l�ԂȂ̂��v�Ƃ����₢�́A���x�́u�^�̍����Ƃ͒N���v�A�u�^�̍�������Ȃ鍑�Ƃ����݂���ɂ͒N���r������ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����v�Ƃ����悤�ɖ{���̍������g�Ɍ������邱�ƂɂȂ����̂������m�|��Q�O�O�T�n
�@�Y�Ɗv���Ɛ����v���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�A���ӎ��������Ȃ��u�Q�O�v�́A�������Đl���`�ɂ���ăi�V���i���Y���ɕ�ۂ���Ă������B�₪�Ă���́A�u�w�N�����̐l�̗���ɗ����čl����\�́x���s�������v�l��~�I�Ȑl�ԁv�m�n���i�E�A�[�����g�P�X�U�X�n�̗ʎY�ɂȂ����Ă��������A���̂��Ƃ͂܂��A��l�ЂƂ肪�Ǝ��ȑ��݂ł���l�Ԃ��A�u�푈�@�B�v�Ƃ��Ắu�������Ɓv�̂��߂ɗ��p�ł��鎑��(���m�A�J���͓�)�Ƃ݂錩�����g�債�Ă��������Ƃ��Ӗ����Ă����B�q�l�O���`���[�h�r������t�����X�̐A���n�}���e�B�j�b�N�̎��l�E�����Ƃ̃G���E�Z�[�[�����P�X�T�O�N�Ɏw�E�����悤�ɁA�u�y���̐l�X�ɑ��镎�J�ɂ��ƂÂ��A���̕��J�ɂ���Đ����������A�������A�A���n���ƁA�A���n�����Ƃ������̂́A�������Ă�Ҏ��g��s��I�ɕϗe�v�����Ă������̂������m�G���E�Z�[�[���Q�O�O�S�n�B���̌�A�l���`�́A�P�W�W�X�N�Ƀp���ōs��ꂽ�����������A���n������Ȃǂ́u�鍑�̓W���v�ŁA�t�����X���o�R���ă��[���b�p�����ւƍL�����Ă������B
���̂悤�ɂ��āA�P�X���I�㔼�A�A���n��`�E�l���`�́A�{���ƐA���n�Ƃ̑��ݍ�p�̂��Ƃɍ��ۓI�Ȓ����Ƃ��Ċm������Ă������B�����āA���̍��ۓI�Ȓ����́A�㔭�̒鍑�ł�����{���܂߁A�n��I�ȍ��ق��ē�����I�ɐ��E�e�n�œ������i�߂��Ă������ƂɂȂ����B
�R�@�l���`�̊w�K�E�͕�ƈڐA
�@������������̖������{�́A���ė̐A���n�ƂȂ�Ȃ����߂ɁA���ۓI�Ȓ����ł���A���n��`�E�l���`�𒉎��Ɋw�K�E�͕킵�A�ڐA���Ă������B�����ېV�̗��N�̂P�W�U�X�N�ɂ́A�a�l�ɂ���ĉڈΓ��ƌĂ�Ă����A�C�k���V�����u�k�C���v�Ɖ��̂��A���{�̗̓y�Ƃ��ċ����I�ɕғ������B���łP�W�V�X�N�ɂ́A�R���͂�w�i�ɗ������������ĉ��ꌧ�Ƃ���(�u���������v)�B���̍ہA�u���{�l�v�u���{�����v�̎��ȉ��̂��߂ɁA��Z�����A�C�k���u��v�u�v�Ƃ������b�e�����͂�����o���Ă��瓯���̑ΏۂƂ����B����ɂ����Ă����l�ŁA�u���t��擪�ɁA�����E�M�E�������w�����x�͈ٕ��Ƃ�������o����A�@�������悤�Ɓv�����m����P�X�X�V�n�B���̌�A�����푈�̗��N�̂P�W�X�T�N�ɂ͐A���n��p���l�����A����ɓ��I�푈�̂T�N��̂P�X�P�O�N�ɂ͑�ؒ鍑�����ē��{�̐A���n�x�z���ɒu���A�鍑�̔Ő}�̂���Ȃ�g����͂����Ă������B���̌�A��p�⒩�N�x�z�ɖ��������A�����ւ́u���Ёv���f���A�����ւ̐��͊g���Ɠ����푈��簐i���Ă������B
�@�Ƃ���ŁA���������A�C�k�A����A��p�ɑ���A���n��`�E�l���`�̎��H�𐳓�������u�ޗ��v������̂��A�����Ɠ������A���{�ɂ����Ă��l�ފw�ł������B�u�l��_�I�l�ފw�v�̉e���������{�̐l�ފw�҂����̓A�C�k�̓��W���̔��@��g�̌v�����̒������s���A�A�C�k����ŕ����ɒx��Ă��邱�Ƃ�������A���̂��Ƃ͉�����p�̐�Z���̏Љ�̎d���ɂ����Ă������ł������m�Ђ낽�Q�O�O�W�n�B�����āA�P�X�O�R�N�ɂ́A���{�̐l�ފw�̑c�E�؈䐳�ܘY���P�W�W�X�N�̃p�������������͕킵�Ĕ��Ă�����T�����������́u�w�p�l�ފفv�ɂ����āA�A�C�k�A����A��p�̐�Z���u���ׁv�́A�u�鍑��`�̍ՓT�v������u�ِl��v�u�ٕ����v�́u��i�v�Ƃ��ĕ��ׂ�ꂽ�̂ł������m����A����Q�O�P�T�n�B
�@���̂悤�Ȏ��ӕ��̐A���n���Ɠ������s���āA�u���I�]�����̓��{�̒n���͍����A���n�_�̌��̏�Ƃ��Ăӂ��킵�����������Ȃ��Ă����v�Ǝw�E����Ă���悤�Ɂm����P�X�X�X�n�A������u���n�v�ł��A�p�˒u����_�������߂̌���A�n�悻�̂��̂������Ă����������╶���ւ̒e���ƒ����ւ̓������i�߂��Ă����B�P�W�W�O�N�Ɏ��R�����^���𗝘_�I�Ƀ��[�h���Ă������m�̐A�؎}�����u���쐭�{�͂�����ĉ䂪�������{�V���ɐ����ׂ邱�ƂɂȂ�Ă��A�p�˂̍����͕p��Ɍ��͂̒������ڂ܂邱�ƂƂȂ�A�n���ɂ͌����Ȃ��͂��������ƂɎ���A�l�X�����ē����]�˂ɐ����A��{�͉v�X����ɁA�n���͖������ցA�����č��݂��n���������ċ��n�ɗ��ꍞ�ނ̐����ƂȂ��B�̂ɍ����͍�������ɍs���A�n���͓��X�ɕn��ɌX����B毂Ɉ����މ��ɔ�v�i�u���ۂ̕��ρv�w������x�P�W�W�O�N�X���Q���j�Ɛ������悤�ɁA�����W���𐄐i���閾�����{�ɂ���ĕx�������E�R�������̂��߂ɒn���̕x��͂��z���グ���A������n�����A���n������Ă������B
�@�����������ŁA�u���n�v�ɂ����Ă��u�ٖ����v�u�ٕ����v�Ƃ��ċK�肷��Ώۂ��m�����n����邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿�A�u���n�v�̐l�тƂ̍�����=���������͂��邽�߂ɁA�u�S���ɎU�݁v���Ă������G�^�g���̐l�����Ƃ��̏W�����u�ٖ����v�u�ٕ����v�Ƃ��ċK�肳�ꂽ�̂������B���Ƃ��A�O�d������ł́A�P�W�W�W�N�̒��������̎��ɁA���G�^�g���̐l�������Z�ޑ��������u�l��E�����v�̍��ق𗝗R�Ɏ��o����A�����I�Ɉꑺ���`�����ꂽ�m����s�P�X�W�R�n�B�����āA�P�X�O�T�N�ɂ͑S���ɐ�삯�ĎO�d���m���L���p�`�̂��Ƃōs��ꂽ�������P����̂��߂̒������ł́A�u���핔���v�Ƃ����ď̂��p�����A�l��̈Ⴂ�A����̈Ⴂ�A�ƍ߂̉����A�ӑāA�c�E�A�q���ϔO�̌��@�A���B�튯�̈Ⴂ�Ȃǂ́u�l��I�E����I�E�����I�E�����I���فv�����Ƃ��狭�����ꂽ�m�O�d��������P�X�V�S�B����Q�O�O�R�n�B�����āA�������P����̒��Ŏ����ꂽ�u��ȑ��݁v�u����ȑ��݁v�Ƃ��錩����u���핔���v�Ƃ����ď̂́A�����Ȃɂ���ē��l�̐����{���ɂ����Ă��s��ꂽ���Ƃɂ��S���I�ɍL�����Ă������B
�@�P�X�O�S�N�ɓ����Ȍx�ۋǒ�����O�d���m���ɓ]�o�����L�����������ɒ��ڂ���ɂ��������̂́A�u���v�̏�ɉ����Ĕ�r�I�������ɔƍߎ҂̑������ׁv�i�w���K�V��x�P�X�O�U�N�P�O���Q�V���j�Ƃ���悤�ɔƍߖh�~�̊ϓ_����ŁA���̂��Ƃ͎O�d���ł̕������P���x�@���哱�Ő��s���ꂽ���ƂɌ����Ɏ�����Ă����m����Q�O�O�R�n�B���̌�A�m�������߂Ăӂ����ьx�ۋǒ��ɂ��ǂ����L���́A�P�X�P�O�N�̑�t�����̑{���̐w���w���ɂ��������B���̎��A��R�@�����ǎ��Ȍ����i���i�@�Ȗ��Y�ǒ��j�Ƃ��āA���̐R���ɂ����Ē��S�I�Ȗ������ʂ������̂��A�L���Ɠ������R���o�g�̕����u��Y�ł������B
�@�P�X�O�W�N�̎w��@�̓����̐��i���ł����������́A�S�������Бn����̂P�X�Q�T�N�ɓ����ȎЉ�Ǔ��ɐݒu���ꂽ�����Z�a���Ƌ���̉�ɏA�C�����m�n�ӂQ�O�O�O�n�B�����Z�a���Ƌ���́A�S�������ЂɑR���Đ݂���ꂽ���̂ŁA��O��ʂ��ėZ�a���Ƃ̘A�������@�ւ̖������ʂ��������A���^�̐��̂��Ƃœ��a�����ɉ��̂����펞���ł́A�����́u�l�I�����v������ɉ����ċ��o����u�����������Ɓv�i��̓I�ɂ͐푈�ɕK�v�ȎY�Ƃւ̓]�ƂƁu���B�v�ږ��j�𐄐i�����m����Q�O�P�P�n�B
�w��@�A�������P����A��t�����A�����Z�a���Ƌ���ƂÂ�������̋O�Ղ̔w�ォ�畂���т������Ă���̂́A�u�S�������Бn�����L�v�ŕ������P����Ɋւ��āu�ޓ��͖��������̗��ł����t���̏��ɋ���킢���B�X�����Ƃ̈�厖�Ƌꗶ�����B���{���ǂ������炩�l�ӂ鏊�������������ꕔ�����P������n�߂��v�Ǝw�E����Ă���悤�Ɂi�w�����x�P�X�Q�Q�N�V���j�A�A���n�̐��ɔ����閯����`�ւ̋����ł������B
�@��t�����ōł������̋]���҂��o�����a�̎R���V�{�s�o�g�̕��w�ҁE���㌒���́u��t�����́A���̊����̃f�b�`�����Ă��B�f�b�`���������l�Ԃ��A��t�Ƃ��������𒅂���ɂ́A���{�Ƃ�������ׂ����݂̍�ׂ��p���v���`�����Ƃ��K�v�ł������B��̗��O�ł���B���̗��O�ɐ^��������Η�����̂��A��ΐ��V���𒆐S�Ƃ����I�B�V�{�̃O���[�v�A����A�I�B�Ƃ���������̍��̗��O�ł���v�Ǝw�E���Ă��邪�m����P�X�V�V�n�A���̗��O�����A�u�������Ƃ̓��������͐A���n��`�ł���v�Ƃ������Ƃł������m����Q�O�O�X�n�B�����āA�鍑�I������`�̒S����ł�����������L����́A�A���n�Z������n�̏����ҁA���Y��`�҂△���{��`�ҁA�ړ�����l�тƁA�ƍߎғ��X�́u�����v�̗\���ɋ����i�R�j�A���̗��O����邽�߂ɂ��܂����g�݂��s�����̂������m����Q�O�O�W�n�B
�@�Ƃ���ŁA��Ɍ����悤�Ɂu�������`������ێ�����邽�߂ɂ́A���Ȃ̊O���݂̂Ȃ炸�����ɂ����Ă���̑��݂��K�v�v�ł���m����Q�O�O�U�n�A���̓����ɂ�����u��̑��݁v�Ƃ��ām�����^�s���n���ꂽ�̂��u���핔���v�ł������B�����āA���̂��Ƃɑ傫�Ȗ������ʂ����̂��A�����ł��u�l��_�I�l�ފw�v�ł������B�P�X���I������Q�O���I�����ɂ����āA�l�ފw�ҁE�l�Êw�҂̒��������́A�|�[���E�u���J�ɂ���ĊJ�����ꂽ���W�v����g�̓����̌v���̎�@��p���āA���G�^�g���̐l�����̐l�ފw�����͓I�ɍs�����B�����̌v���̌��ʁA���G�^�g���̐l�����́A��p�̐�Z���u���ׁv�Ɠ��n���̃}���[�n�̐l��ł���A���݂ɂ܂ŌŗL�ȕ������`�`����`����l��W�c�ƈʒu�Â����m���Q�O�P�P�n�B���̒����̒�����O�q�����e�n�̕������P����͐̕V���Ɍf�ڂ���đ傫�Ȕ������ĂсA���G�^�g���̐l�������u�ٖ����v�u��v�u����v�Ƃ������������O�̊Ԃɒ蒅���Ă������B�������āA�]�ˎ���́u�˖��v�ɑ��鍷�ʂ́A�������Ƃ̌`�����i�ނȂ��ŁA�������ʂɎp��ς��A�����܂ő�������퍷�ʕ���(�ȉ��A����)���a�������B�����ɁA�����̐l���`���w�K�E�͕�E�ڐA�����������ʁA���Ȃ킿�O�ߑ�̐g�����ʂɋߑ�l���`��ڂ������������ʂ��A�V�c���̊m���Ɩ��ڂɌ��т��Đ��������̂������B
�@�V�c�������������̒��S�ɂ�����ꂽ���ƂɊւ��ẮA���쒷�v�����u�����I�ȏ@���������킪���ɂ����Ĉꍑ�̓Ɨ����낤�������˂Ȃ��L���X�g�������ۂ���Ƃ���A����ɑ�����̂Ƃ��Ă͓V�c���������肦�Ȃ��v�ƍl����ׂ��ł���A�V�c���́u���W���[���Ƃ��ĈڐA���ꂽ�������ƍő�̓�_�̍����ł���A�܂��������{�^�������Ƃ̑n�o�m�����n�ł������v�Ǝw�E���Ă���m����P�X�X�T�n�B
���{�ɂ�����u�q��v�̕����̗��j���ӂ܂��đn�o�m�����n���ꂽ�V�c���́A�V�c�̑ɂƂȂ鑶�݂�K�v�Ƃ��Ă����m�ĒJ�P�X�X�P�n�B�����ŋߑ�ɂ����ām�Ĕ����n���ꂽ�̂����G�^�g���̐l�����ł���A����Ƃ��Ă̕������P�����ʂ��āu���핔���v���m�����^�s���n���ꂽ�B�����ĕ������ʂ́A�O�d���̕������̕n���ƕs�����p�̐�Z���u���ׁv�ɂȂ��炦�ė����K���������悤�ɁA����{�鍑�̐A���n�x�z���g�債�Ă������Ƃɂ���āA����ɑ�������Ă������̂������m�Ђ낽�Q�O�O�O�n�B
�@�����N�w�҂̃n���i�E�A�[�����g�́A�P�X���I���ɂ�����u�@���I�ȃ��_���l�����Ƃ͈قȂ锽���_����`(���Z����`�A�A���e�B�Z�~�j�Y��)���Љ����̓�����I�Ȗ��ƕ��s���Č��ꂽ�B�i���j�鍑��`�ƂȂ��Ă����i�K�Ō��������Ƃ������Ƃ����ƂȂ�v�Ǝw�E���Ă��邪�m�n���i�E�A�[�����g�P�X�V�Q�|�P�X�V�S�A���Q�O�P�S�n�A�������ʂɊւ��Ă�����Ɠ��l�̂��Ƃ�������ł��낤�B���Ȃ킿�A�������P���W�J���ꂽ�Q�O���I�����́A���I�푈�̏����ɂƂ��Ȃ��ē��{�̐A���n�x�z���g�債�A�u�ꓙ�����v�Ƃ��Ă̈ӎ������g���Ă����B�u�w�ꓙ�����x�Ƃ��č��ې��E�ɑΓ��Ɉ����邽�߂ɂ́A�����̂Ȃ��Ɉ�l�O�ł͂Ȃ��A�Ȃ葹�Ȃ��̓��{�l��K�v�Ƃ����v�m����Q�O�O�W�n�B�����́u�Ȃ葹�Ȃ��̓��{�l�v�́u�`���I�ɂ͓��{�l�ł��������A�l�퍷�ʂ̑ΏۂƂ��ꂽ�l�X�v�ł���A�A�C�k�≫��l�Ɠ��l�ɁA���������܂��A�u�ꓙ�����v�Ƃ��Ă̎��ȉ��̂��߂́u���n�v�ɂ�����u�Ȃ葹�Ȃ��̓��{�l�v�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ�̂ł������B
�@�������A�u�m�����^�s���n���ꂽ���͉̂��ł����̉\�ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�����������������ׂ���ԑ�Ȗ₢�Ƃ́A���̏ꏊ�Ŏ��ɉ���n������̂��Ƃ������Ɓv�ł���m���r���E�c�E�f�E�P���[�Q�O�O�V�n�A���̂��߂Ɂu�N���Č���[�閾�����v�i�����Бn����ӏ��u�悫���ׂ̈Ɂv�j�Ƃ����Ăт����̉��ɐ����Бn���̏������i�߂�ꂽ�B
�S�@���p�Ƒ��̒�����
�@��̎O�d���̕������P����̂��߂̒������ɂ́A�ʏ�l�ԈȊO�ɗp����u�ɐB�v�Ƃ������t���g���A���G�^�g���̐l�������u�b�v�ɋ߂����݂Ƃ��ĕ`����Ă����m�O�d��������P�X�V�S�B����Q�O�O�R�n�B�G���E�Z�[�[���́u�A���n������҂́A����̖ƍߕ���^���邽�߂ɁA����̓��ɏb������K����g�ɂ��A������w�b�Ƃ��āx �����P����ς݁A�q�ϓI�ɂ͎���b�ɕϖe���Ă����̂��Ƃ������Ƃ��ؖ����Ă���B�����K�v���������̂́A�A���n���̂���������p�A���̔������̏Ռ��ł���v�ƌ���Ă��邪�m�G���E�Z�[�[���Q�O�O�S�n�A�����l�Ԃł���퍷�ʕ����̐l�������u�b�v�̂悤�Ɉ������ƂŁA���҂̐S�ɑ���u�����I�z���́v��r�����A�u�ނ玩�g���b�ɂȂ��Ă������v�̂������i�S�j�B
�؍������Ɠ������N������t�����̋]���ɂȂ����K���H���́A���I�푈�ɍۂ��ď������u���m�𑗂�v�Ƃ����_�e�Łu���N�͍���l���E���ׂɍs���A�ۂ���ΐl�ɎE����ׂɍs���B��l�͒m��A������ɏ��N�̊��ɂ��炴�邱�Ƃ��A�R��ǂ����m�Ƃ��Ă̏��N�́A�P�Ɉ�̎����@�B�Ȃ�v(�w�����V���x��P�S���A�P�X�O�S�N�Q��)�Ǝw�E�������A�鍑���{�̑ΊO�N�����{�i�����邱�̎����ɁA�u�푈�@�B�v�ł������������ƂɁu�ӂ��킵�����݁v=�u�����@�B�v�ɖ��O�͕ϐg�������悤�Ƃ����̂������m����Q�O�O�O�n�B
�@�����������Ƃ��炷��ƁA�����Ƃ́A���O���u���Ƃɂӂ��킵�����݁v�ł���u�����v�ɕϐg�����邽�߂̑��u�̈�Ƃ��đn�o���ꂽ�Ƃ����邾�낤�B�������Ēa�������u�����v�́A�u���̕i����������A�������̉B�ꂽ�{�\���A�×~���A�\�͂��A�l��I�������A�ϗ��I��ʐ����Ăъo�܁v����A�܂��A�u�����v�ݏo����Ă邽�߂ɑn�o���ꂽ���������A��������ł��镔�����P����ɂ���āA�u���|�A���A���т��A���]�A��]�A���l�������I�݂ɐA���t����ꂽ�v�̂������m�G���E�Z�[�[���Q�O�O�S�n�B
�@���̂悤�ɁA�������P����ɂ��A���n��`�E�l���`�̎��H�́A���ʂ����ҁA���ʂ���҂̑o�������p�Ƒ������������A���̈Â��ł̒�����S�������Ђ͋N���������Ă����B�S�������Бn���̃����o�[�̈�l�A���쏬���́A�n���̑O�N�̂P�X�Q�P�N�Q���R���ɒ鍑������̎�Âɂ���ĊJ���ꂽ��Q��Z�a���̉��ɂ����āA���������u�����v�ƋK�肵���u�����v���u���������c�v�̖��ł܂����B���̖`���ɂ́u��疯���̑c��͍ł���Ȃ鎩�R�ƕ����̊��҂ł���A�����s�҂ł������B�����čł��̑�Ȃ�}���҂ł������B�䓙�͂��̑c��̌��������������ł���B���␢�E�̑吨�͖��������̋ŏ��𗐑ł�����A�䓙��䢂��K�R�N���ĕ����I�Љ�g�D�̐ꐧ������X�����̐�ΓI�w�́x��ւ��āA�䂪�����̉������悵�Ȃ���Ȃ�ʁv�Ə�����Ă����B
�@�����āu�S�������Бn�����L�v�Ɂu���B�헐�̎Y���Ƃ��Đ��E�̈�p���痐�ł��ꂽ���������̋ŏ��́A��X�����ɋ����h����^�����B�t������������̉�����X�����̎��S�ɋ������H�A�������̗L���҂͑o��������ėx�苶�����B��L�]�N�̊Ԃ̋��]�̓z�ꐶ������E����H�͗������Ɩ����Ɋ�B�����̌����͖��������B�������O�ڂ���v�z�̒����͐N�����ĐZ�����߁v�ƋL����Ă���悤�Ɂi�w�����x�P�X�Q�Q�N�V���j�A���ې����ւ̉s�������������N�����ɂ���āA�P�X�Q�Q�N�R���R���A�S�������Ђ͑n�����ꂽ�B�P�X�Q�R�N�P�P���Ɍ������ꂽ�S�������АN�����𗝘_�I�Ɏw����������������u���E�l���̂S���̂R�͐B���n�Ȃ������B���n�̏�Ԃɂ���B�����Ă����̓z�ꉻ�̒n�ʂɒu���ꂽ�P�R���̖��̕s���ɐS��ɂނ���̂́A�Ⴊ���ɌÑ�z����霂���R�O�O�����E�̑��݂��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�ʁv�ƁA�����̏Ɓu�B���n�Ȃ������A���n�̏�ԁv�Ƃ��d�˂ĂƂ炦�Ă����m�����P�X�Q�R�n�B
�@�P�X�P�V�N�̃��V�A�v���A��ꎟ���E����̖��������_�̒A�P�X�P�X�N�ɓ��{���{���p���u�a��c�ɒ�Ă����l�퍷�ʓP�p���ẮA�A���n�����ꂽ�n��E�l�X�ɑ傫�ȉe����^�����B�p���u�a��c�̂��Ȃ��A��P��̃p���E�A�t���J��c�����n�ŊJ���ꂽ�B�����g�D�����A�����J�̍��l����^���̎w���ҁEW�EE�EB�E�f���{�C�X�́A���O���̍��l���ʂ��i���{��`���ɂ��S���E�I�ȗL�F�l��}���̈�Ƃ��ĂƂ炦�A���O���̍��l�̉^���𐢊E���̗L�F�l��̓����̒��Ɉʒu�Â��Ă����m�|�{�Q�O�P�Q�n�B�C���h�ɂ����Ă̓C�M���X�̐A���n�x�z�ɑ��āA�K���f�B�[����\�́E�s���]�^�����J�n���A���A�W�A�ł́A�P�X�P�X�N�A���{�ɕ������ꂽ���N�łR.�P�Ɨ��^�����A�����ł͂T.�S�^�����N�����B���{�ł��A���n��`�E�l���`�̖\�͂ɎN����Ă����������E���쏬�����l�퍷�ʓP�p�Ɩ��������ɂ��������������Đ�́u���������c���v���܂��A�����đS�������Ђ��n�����ꂽ�B����ɂP�X�Q�R�N�ɂ́A�A�C�k�������ւ�����߂��A���̐��E�ς��L�����ɓ`����o���_�ƂȂ����m���K�b�w�A�C�k�_�w�W�x���o�ł��ꂽ�i�T�j�B
�@���̂悤�ɂP�X�P�O�N�ォ��Q�O�N��͔��A���n��`�E���l���`�̓��������E�I�ɍ��g���Ă������A���̈���Ń��[���b�p�ł͐i���R�Ƃ��ăh�C�c�ɓ������ꂽ�A�t���J���ɑ��鍷�ʂ��L�܂�A�P�X�Q�O�N���ɂ̓A�����J�ɂ����Ă̓N�\=�N���b�N�X=�N�������}���ɑ䓪���Ă����m�n�ӂP�X�X�V�n�B���{�ł��S�������Ђ��������ꂽ���N�̂P�X�Q�R�N�R���ɓޗnj��ō��ʔ����ɑ���Ӎ߂��߂����đS�������ЂP�O�O�O�l�Ƒ���{������P�O�O�O�l�Ƃ��Λ����Փ˂��������i�������������j������A�X���ɂ͊֓���k�Ђɂ����钩�N�l�s�E���������B�P�X�Q�U�N�P���ɂ́A�O�d���ؖ{���i���F��s�j�Ńg���l�����ݍH���ɗ��Ă������N�l�J���҂ɑ���n���̍��R�l�𒆐S�Ƃ����Z���ɂ��s�E�����i�ؖ{�����j���N�����B�A���n��p�ɂ����Ă��u���{�̂P�X�P�O�N��`�Q�O�N��́w�f���N���V�[�x�i�C���y���A���E�f���N���V�[�j�̎���́A���{�l�ɂ���p���Z���E�C�̎���ł������v�m���P�X�X�U�n�B
�@�����������E�I�Ȍ��ۂɂ��āA�u�W�c�I�q�X�e���[�ȂǂƂ������̂ĂȂ��A�l��Η��̖\�͐��̔����̐��E�I�ȓ������Ƃ��čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���v�Ǝw�E����Ă���悤�Ɂm�n�ӂP�X�X�V�n�A�P�X�P�O�N�ォ��Q�O�N��́A�A���n��`�E�l���`�����������悤�Ƃ��铮���Ƃ����p�₵�悤�Ƃ��铮���Ƃ̑Η������E�I�Ɍ������Ă������j�I�ȓ]��_�ł������Ƃ����悤�B
���̂悤�Ȑ��E�I�ȘA���̒�����A�A���n��`�E�l���`�ɔ�����u���A�W�A�v���v�m�e�b�T�E���[���X�E�X�Y�L�Q�O�O�W�n�̈�Ƃ��āA�S�������Ђ͌������ꂽ�̂������B���̑n�����́u�錾�v�ł́u�ߋ������I�ԂɎ�X�Ȃ���@�ƁA�����̐l�X�ɂ���ĂȂ��ꂽ�䓙�ׂ̈̉^�����A�����̗L����ʂ����Ȃ����������́A�v���̂��ׂĂ���X�ɂ���đ��̐l�X�ɂ���Ė��ɐl�Ԃ�`������Ă������ł������̂��B�����āA���ꓙ�̐l�Ԃ邩�̔@���^���́A�������đ����̌Z�������������Ƃ�z���A���ۉ䓙�̒����l�Ԃh���鎖�ɂ���Ď���������Ƃ���҂̏W�c�^�����N������͔J��K�R�ł���v�ƁA�������P����ɂ���Ă����炳�ꂽ�u���v�����ꂩ��ᔻ���A���́u���v���~�����߂ɑS�������Ђ��������ꂽ���Ƃ������i���Ă����B
�@�u�錾�v�ɂ͖{���U�O�T�����Ɂu�l�ԁv�Ƃ������t���P�O����g���Ă������A���̍Ō�́u�l�̐��̗₽�����A����Ȃɗ₽�����A�l�Ԃ�鎖�����ł��邩���悭�m���Ă����X�́A�S����l���̔M�ƌ����苁��]������̂ł���B�����Ђ͂������Đ��܂ꂽ�B�l�̐��ɔM����A�l�Ԃɂ���v�Ƃ����L���Ȍ��t�Ō���Ă����B�u�錾�v�̒��́u�l�ԁv�Ƃ������t�́A��ʓI�ȃq���[�}�j�Y������o�����̂Ƃ������A�������ʂɂ���đ傫�ȋ�Y�ɂ����Ȃ܂ꑱ�����̌��ɍ����������҂̐S�ւ́u�����I�z���́v�Ɛl�ԉ���ɑ��錃�����~�����炩��o�����̂ł������B���̈Ӗ��ŁA�u�錾�v�́A�悭������悤�ȃt�����l���錾�␢�E�l���錾�ɕC�G������̂Ƃ������i�U�j�A�A���n��`�E�l���`�ɂ���Ė����⍑������r�����ꂽ�����҂����ɂ��u�l�ԉ���錾�v�̐�삯�ł���A��O���E�̓������߂��������̂��ے��������t�ł���u�^�̖��͐l�Ԃ����������Ƃ��v�m�t�����c�E�t�@�m���P�X�U�X�n��A�A�t���J�n�A�����J�l�̓����̃X���[�K���ł������u�u���b�N�E�C�Y�E�r���[�e�B�t���v�ւƂȂ����Ă������̂ł������Ǝv���B
�@�������Đ����Ђ́A���́u�j�́v�Ɂu�䓙�͐l�Ԑ��̌����Ɋo�����l�ލō��̊����Ɍ����ēːi���v�ƋL�����悤�ɁA��l�ԉ����ꂽ�������g���A�����ĐA���n��`�E���ʎ�`����ʉ�������ꂽ�u�����v���A�����������ւƕ��ݏo���Ă������̂ł������B���̐�ɂ͊O������̍��d�E����E�e���A�����Ɨ��݂������u�Ԃ̑Η��⌠�͓����Ƃ�������ȏ�����A�����āu�Ȃ葹�Ȃ��̓��{�l�E�����v�Ƃ����ʒu���������u��l�O�̍����Ƃ��ĔF�߂�ꂽ���v�Ƃ�����]�䂦�ɁA�u�����ҁv�u�鍑�I������`�ҁv�֕Ґ������Ƃ����傫��㩂����Ƃɂ���Ďd�|�����Ă����i�V�j�B
�@�S�������Ђ̑n���҂������v���`���������̋���ȖڕW�́A���Ô��������т����ᔻ�����悤�ɁA�펞���̐N���푈�ւ̋��͂Ɩ������ʂւ̉��S�A�I�[���E���}���X�����ɏے������悤�Ȑ��ɂ����鍑����`�I�ȉ^���̌p���Ȃǁm���P�X�X�S�n�A����̎コ�⌠�͂̍��d�ɋ����ē����ŕ���������Ĕj�]���Ă������ƌ����邩������Ȃ��B�����A���E�����������Ƃ̂Ȃ����z�̎������߂������u�u�v�́A�����ď��������Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��A���ɂ����鋷�R�����A�����^���Ȃǂ̕����^���̒��ɐ���������Ƌ��Ɂm�����Q�O�O�V�A����P�X�V�X�n�A���܂��܂ȋ��E���Čp������Ă����B
�@�u��Q�ҁv����^�������[�h���Ă�����l�ł���q����i�����c�������@�l��ߕ������\�����j�́A���Ƃ̕������ŁA�S�������Бn�����́u�錾�v�Ƃ̏o��ɂ��āA�u�ア����̂��̂��͂����Ƃ����̂͑�ςȂ��ƁB���Ō����قNJȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�����А錾�Łw�l�ԂɌ�����x�ƁA�ア����ɒu���ꂽ������A���ꂾ���̗͂������t���������B���̂��Ƃɂ��̂��������������v�ƌ���Ă���B���������o���ʂ��āA�q�����́u���������Ƃ����A������������v�Ƃ����咣��W�J���A�u�i�l�Ԃ̐S�́j�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃɐ��܂��B�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃ�������Ȃ��B�����̊Ԃɂ��A�A���Ƃ̊Ԃɂ��A�����A���[�̏��Ƃ̊Ԃɂ��S�͐��܂�o��B������A�w�l�ԁx���Č����낤�ˁv�Ɓm�q���P�X�X�T�n�A���E�̊�]�̂��߂ɐl�ԉ�������߂ē������l�����Ɠ����悤�ɁA�����̐l�Ԃ����l�ȉ��l�������Ȃ��狤�����A�n���K�͂ő��݂Ɉˑ��������Ȃ��琶���Ă���Ƃ������Ƃ��咣�����̂������i�W�j�B
�@�����A�C�O�ŕ��͍s�g�����邽�߂́u���h�R�v�̑n�݂ƈ��S�ۏ�֘A�@�Ă̐����̓������A�����̍ĉғ��ƗA�o�̐��i�Ɨ��݂Ȃ��狭�d�ɐi�߂��Ă���B�܂��A���������ƌ��т��āA�w�C�g�E�X�s�[�`���������Ă���B���̂悤�ȐA���n��`�E�l���`�̌p���̂��ƁA�Q�O�P�T�N�V���P�O���A����O�ň��S�ۏ�֘A�@�Ăɔ�����R�c�s�����s��ꂽ�B���̒��ŁA��l�̏��q�吶���u�l�̒ɂ݂ɖ����o�ŁA�v�l��~����l�ԂɂȂ肽���Ȃ��B�����琺���グ��v�Ɛ錾���A�Q���҂��犽�����オ�����i�w�����V���x�Q�O�P�T�N�V���P�Q���j�B�[��������u�l�Ԃ̖��p���v�ɑ��铬���́A�n���N����Ċg����n�߂Ă���̂ł���B
��
�i�P�j���N�i�Q�O�P�T�N�j���T�O�N�ڂɂ����铯�ΐR���\�i�����ɂ́u���a�n��Ɋւ���Љ�I�y�ьo�ϓI�������������邽�߂̊�{�I����v�ɑ��铚�\�j�́A���̌�̓��a�s���̊�{�I�w�j����������ʂ����A���݂��A���{�A�n�������c�̂͂������^���c�̂��ϋɓI�]����^���Ă���m��������E�l���������ҁw�������E�l�����T�x����o�ŎЁA�Q�O�O�P�N�n�B�������A���ΐR���\�̖{���́A�����̏��u���n�Љ�̑e��ƕ����Љ�̔ߎS�������˂��Ȃ����n��v�ƂƂ炦�A�u�������v�u�ߑ㉻�v�ɂ���Ă��̖��́u�����v���͂��낤�Ƃ�����������ł������B���̈Ӗ��ŁA���ΐR���\�́A���N�ɒ������ꂽ���؊�{���A�P�X�U�R�N�T���ɋN�����l�ߎ����ł��鋷�R�����Ɠ������A���x�o�ϐ������́u�����v�̍ĕ҂̖��Ƃ��ĂƂ炦�Ă����K�v������Ǝv���B�܂��A�P�X�U�S�N�ɍ��O���Ő��肳�ꂽ�������@�ɂ́u�^�������Y��`�̉e������藣���Ă����v�Ƃ����Ӗ����B����Ă������m�|�{�Q�O�O�P�N�n�A���ΐR���\�₻�̋�̉��̂��߂ɐ��肳�ꂽ���a�Ɠ��ʑ[�u�@(�P�X�U�X�N)�Ɋւ��Ă��A�u�����}���{�����̒�ӂ̍ł��Ԃ��݂ȗ͂����W�c���Ǘ����A����������@�Ƃ��āA���̓��a�ƂƂ������̂����e���Ă����̂ł͂Ȃ����ƁA���͍l���Ă��܂����B���a�Ɠ��ʑ[�u�@�A�n����P�����ʑ[�u�@�̒��ɂ��鎩���}���̐����I�ǂ݂Ƃ������̂��A���͌���v���̖��ƊW������Ǝv���܂��v�Ǝw�E����Ă���m�F��P�X�W�R�n�B���ΐR���\�⓯�a�Ɠ��ʑ[�u�@�́A�P�X�T�O�N��㔼����U�O�N�ɂ����ċΕ]�����A���ۓ����A�O�r������ϋɓI�ɓ���������������������Ƃɉ�����邱�Ƃ��˂�������̂ł������Ƃ����悤�B
�i�Q�j�u�����j�����v���͂��߂Ƃ��鍷�ʎj�����҂̎p���̖��Ɋւ��āA��������^��������Â��Ă����������ʂ̖����k�Ȏ��؍�Ƃɂ���Ă��т����ᔻ�������Ô����́A���̔ᔻ�͕������������A���̂��Ƃ�����܂Ŗ��ĂɎw�E���Ȃ�����������(���{�l�S��)�Ɍ�����ꂽ���̂ł���ƂƂ��ɁA���{�l�̖������ʂɂ�������ᔻ�ł��������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���m���P�X�X�S�n�B�������A���̔ᔻ�������������҂����╔������^���ɂ���������l�����ɂ��āA�u���̌���A�����̂قƂ�ǂ͂������Â��邾���łȂ��A�Ȃ����͏H��Øa�̂悤�ɁA�킽���̑S�������Ђɂ�������w�C���[�W�x��w���ҁx�ɂ��ċ������������̂�����v�Ǝw�E���Ă���悤�Ɂm���P�X�X�U�n�A�����̔����͖��Ăł͂Ȃ�����̈������̂ł������B���쒷�v���͐A���n��茤���ɂ��āu�A���n���̌����قnj����҂̗���m�ɂ��炯�o���A���m�Ɏ������Ƃ��v������錤���͏��Ȃ��Ǝv���܂��B�i���j�����̗����ʒu�Ȃ��邱�ƂȂ��A����
�@�I�Ȍ������ʂ�ςݏグ�Ė������Ă���K���Ȍ����҂�����ƁA�ǂ��Ή����Ă悢�̂������Ă��܂��܂��B���邢�͋t�ɁA���Ȃ̓��Ȃ��A���n��`�ɖڂ��ނ��āA�A���n��`�̕s���Ɖ��Q�������т��Ă�A���`�̖����I�Ȍ����҂̑��݂��ǂ��l����悢�̂ł��傤���v�Ɣ������Ă���m����Q�O�P�R�n�B���ȉ���E�l�ԉ���Ƃ������@�������������u�����j�����v�ɂ��Ă����l�̂��Ƃ�������Ǝv���B
�i�R�j�h�J�W�O���́A�����́u���̂悤�ȍ��̘_�̂��Ƃł́A���_���v�z�A���Y��`�́A�����Ƃ�����ׂ��G�ł���B�Ȃ��Ȃ�A���̂��ꎩ���ɑ���U����ژ_�ނ��̂ł��邩��ł���B���̔����_���v�z�Ƃł��ĂԂׂ����̂́A���������łȂ��A�������܂߂��l�X�Ȑl����������ċ��L����Ă����v�Ǝw�E���Ă���m�h�J�Q�O�P�R�n�B�����ɋ������Ă���u�����v�Ƃ́A�����ȏ����Ƃ��ĕ������P������w�����������吳�̎Љ�ƉƁE�����K���̂��Ƃł���B���̈Ӗ��ŁA�������P����i�̂��̒����Z�a���Ƌ�����j�́A�u�����v�̌����ƌ��Ȃ��Ă����������u�������v���邱�ƂŁA����ł��Ă��̉��E�ݎ���Ă��܂��Ƃ������Ƃ��˂�������̂ł������B
�i�S�j���̖��ɂ��āA��A�t���J�o�g�̕��w��J�E�M�E�N�b�c�G�[�́A�����w�����̂��̂��x�̓o��l���ł����ƁE�G���U�x�X�E�R�X�e�����u�����l�ԁA�_�̎��p�Ƃ��đn��ꂽ�l�Ԃ��A�����̂悤�Ɉ������ƂŁA�ނ玩�g����b�ɂȂ��Ă������̂ł��v�A�u���̑��݂̗���ɂȂ����l���Ă݂���͈͂Ɍ��E�͂���܂���B�����I�z���͂Ɍ��E�͂Ȃ��̂ł��v�ƌ�点�Ă���mJ�E�M�E�N�b�c�G�[�Q�O�O�R�n�B
�i�T�j�u��̓H�~��~��܂��ɁA���̓H�~��~��܂��Ɂv�Ƃ����u���̐_�̎���̂����w�v�ł͂��܂�w�A�C�k�_�w�W�x�́A�u��؈ꑐ�ɗ��j�����݂��A�F�����Ԃ�����j�����A�C��������j��ۑ�����悤�ȁv�A�C�k�̐��E�ς��\������̂ł���m�{���Q�O�O�T�n�B���q����u��Q�ҁv����^���̖q����̒�N�Ƃ����ʂ���A���n��`���r���������E�ρE�l�Ԋς��w�Ԃ��Ƃ��A�R�D�P�P���o�������������ɋ������߂��Ă���Ƃ����悤�B
�i�U�j����S�q���́A�t�����X�̐l���錾(�P�V�W�X�N)�́u�j���̌����錾�v�ł���A�l���錾�Ƃ��̃p���f�B�Ƃ��Ď��M���ꂽ�����錾(�P�V�X�P�N)�Ƃ��r�ΏƂ��ēǂނ��Ƃɂ���āA�u�l�ԁE�s���E�����̗��O���ǂ̂悤�ɂ��ď����̕s�݂̂܂ܑn���A����������v�������������邱�Ƃ��ł���v�Ǝw�E���Ă���m����Q�O�O�O�n�B
�i�V�j�u�Ȃ葹�Ȃ��̓��{�l�E�����v�ƋK�肳�ꂽ���䂦�ɁA�u���{�����v�ł��邱�Ƃ��ؖ����邽�߂ɁA�u�����ҁv�Ƃ��Ė��B�N���ւ̉��S�Ȃ��̐A���n�x�z�̉��Q�҂ɂȂ��Ă��������ɂ��ẮA���ĎO�d�������Ђ̎w���҂ł�������c���s�����グ�čl�@�����m�{�{�Q�O�O�Q�A�Q�O�P�Q�n�B
�i�W�j���m�̂悤�Ƀn���i�E�A�[�����g�́A�u�l�Ԃ̕������A�l�Ԃ̖����̍��ِ��v�A�u�l�Ԃɂ��l�Ԃ̖��p���v�̖��ɂ��Đ��U�������ĒNjy�����m�n���i�E�A�[�����g�P�X�V�Q�\�P�X�V�S�n�B
�y�Q�l�����z
�F���g�u���R�����S�N�\���{�ɂ����鍷�ʂ̍\���Ǝ��R�����^���\�v�i�F���g�E���X���M�w���j�ɂ�����l�ԂƊv�V�\���R�����ƕ�������\�x������������L�����A����A�P�X�W�R�N�j�B
�G���E�Z�[�[���i����K����j�w�A���m�[�g/�A���n��`�_�x���}�Ѓ��C�u�����[,�Q�O�O�S�N�B
���쐭���u����̌o���v�w���j�w�����xNO.�V�O�R�i�P�X�X�V�N���j�w��������j�A�P�X�X�V�N�P�O���B
���Ô��w�����^���j�����y�������ʔᔻ�z�x�����掺�A�P�X�X�S�N�B
���Ô��w�̋��̐��E�j�@����̃C���^�[�i�V���i���Y���ցx�����掺�A�P�X�X�U�N�B
����݂ǂ�w�n��j�̂Ȃ��̕�������\�ߑ�O�d�̏ꍇ�x����o�ŎЁA�Q�O�O�R�N�B
����݂ǂ�u�l���`�ƕ������ʁv�i�|��q�ҁw�l��T�O�̕��Ր���₤�@���m�I�p���_�C�����āx�l�����@�A�Q�O�O�T�N�j�B
����݂ǂ�w�ߑ㕔���j�@�������猻��܂Łx���}�АV���A�Q�O�P�P�N�B
����݂ǂ�E����L�w���ʂ̓��{�ߌ���j�@��ۂƔr���̂͂��܂Łx��g���X�A�Q�O�P�T�N�B
���䒼���w��]�ƌ��@�@���{�����@�̔��b��̂Ɖ����x�ȕ��ЁA�Q�O�O�W�N�B
J�E�M�E�N�b�c�F�\�i�X�S��q�E���֎����j�w�����̂��̂��x�匎���X�A�Q�O�O�R�N�B
�ĒJ�čO�w�Ȋw�ᔻ���獷�ʔᔻ�ցx���Ώ��X�A�P�X�X�P�N�B
�h�J�W�O�u����{�鍑�̌Y���v�z�ɂ�����w�����x�Ɓu�O���v�F�Y���v�z�j�m�\�g�v�i�w�����w�|��w�I�v�@�l���Љ�Ȋw�n�U�x��U�S�W�A�Q�O�P�R�N�P���j�B
�����u�Q�O���I�����ɂ�����A�J�f�~�Y���ƕ������F���\���������̓��{�l��_�Ɣ퍷�ʕ����������̌�������v�w�Љ�Ȋw�x��S�P����P���A�Q�O�P�P�N�T���B
��������u���ꕔ���̗��j�Ɛ����^���v�i���Y�a���ҁw�v�z�̊C�ւP�W�@�������l�̐��Ɍ�����x�Љ�]�_�ЁA�P�X�X�P�N�j�B
�|��Y�u�l��^�����^�鍑��`�\�P�X���I�t�����X�ɂ�����l���`�l�ފw�̓W�J�Ƃ��̔ᔻ�\�v�w���������w�����ٌ����x�R�O(�P)�A�Q�O�O�T�N�B
�|�{�F�q�uW�EE�EB�E�f���{�C�X�Ƒ����̌������^���v�w����c��w��w�@���w�����ȋI�v�x�S�U�A�Q�O�O�P�N�B
�|�{�F�q�uW�EE�EB�E�f���{�C�X�ƃp���E�A�t���J�j�Y���v�w����c��w��w�@�����ȋI�v�x��S�����A�Q�O�P�Q�N�B
�e�b�T�E���[���X�E�X�Y�L�u���N���������߂铌�A�W�A�̍\���v�w�����V���x�Q�O�O�W�N�Q���Q�U���B
���㌒���u���̒��̓��{�l�\��ΐ��V���v�i�w�g�x�P�X�V�V�N�S�����B�̂��w���㌒���G�b�Z�C��W�m�t�E�{�[�_�[�сn�x�P���ЁA�Q�O�O�P�N�����j�B
�����q�w�t���̎u���@�����q����镔������^�����L�x�����[�V�ЁA�Q�O�O�V�N�B
���쒷�v�u���{�^�������Ƃ̌`���\��r�j�I�ϓ_����ցv�i���쒷�v�E���{�G���ҁw�����E�������̍������ƌ`���ƕ����ϗe�x�V�j�ЁA�P�X�X�T�N�j�B
���쒷�v�u�����j�w�ƍ������Ƙ_�v�i���j�w������ҁw�����j�w�čl�x�؏��X�A�Q�O�O�O�N�j�B
���쒷�v�w�q�V�r�A���n��`�_�x���}��,�Q�O�O�U�N�B
���쒷�v�u���܂Ȃ��A���n��`�������̂��[�A���n��`�_��[�߂邽�߂Ɂv�i���쒷�v�E�����G���ҁw�O���[�o���[�[�V�����ƐA���n��`�x�l�����@�A�Q�O�O�X�N�j�B
���쒷�v�w�A���n��`�̎�����āx���}�ЁA�Q�O�P�R�N�B
����S�q�w�ߑ㍑�ƂƉƑ����f���x�g��O���فA�Q�O�O�O�N�B
�n���i�E�A�[�����g(��v�ۘa�Y��)�w�C�F���T�����̃A�C�q�}���@���̖}�f���ɂ��Ă̕x�݂������[�A�P�X�U�X�N�B
���@�w�S�̎�`�̋N���x�S�R���A�݂������[�A�P�X�V�Q�|�P�X�V�S�N�B
����͔V�w�W�����i�͂��߁x���U�����ЁA�P�X�V�X�N�B
�Ђ낽�܂����u����@���{�ߑ�Љ�̍��ʍ\���v�i�w���{�v�z�̌n�Q�Q�@���ʂ̏����x��g���X�A�P�X�X�O�N�j�B
�Ђ낽�܂����u���ʂ͋ߑ�̎Y���v�w��������x��S�V�O���A�Q�O�O�O�N�U�����B
�Ђ낽�܂����w���ʂ���݂���{�̗��j�x����o�ŎЁA�Q�O�O�W�N�B
�t�����c�E�t�@�m���i�C�V�═�E�������v��j�w�����畆�E�������ʁx�݂������[�A�P�X�V�O�N�B
�q�����w�����s���R�łǂ��炪���R���x�i�͍��u�b�N���b�g�j�͍��������猤�����A�P�X�X�T�N�B
����s�w����s�j�x��P�T���q�j���ҁE�ߑ�i�Q�j�r�������[�A�P�X�W�R�N�B
�O�d��������ҁw�O�d�������j���W�x�ߑ�сA�O�ꏑ�[�A�P�X�V�S�N�B
�{�{���l�u��O�E�풆�̎O�d����Ə�c���s�v�i�H��Øa�E�������ҁw�ߑ���{�Ɛ����Ёx����o�ŎЁA�Q�O�O�Q�N�j�B
�{�{���l�u�O�d����̓s�s�������o�������ߑ�v�w������������x�mo�D�P�X�S�A�Q�O�P�Q�N�R���B
�{���N��w�|�X�g�R���j�A���Y���x��g���X�A�Q�O�O�T�N�B
���v���q�w�n���i�E�A�[�����g�@�u�푈�̐��I�v���������N�w�ҁx�����V���A�Q�O�P�S�N�B
���r���E�c�E�f�E�P���\�i���c���s�E����������j�w�Q�b�g�[��s������[�A�����J�ɂ�����s�s��@�̕\�ہx�k���ЁA�Q�O�O�V�N�B
�n�ӌ��O�u�w��ƍ��Ɓ@�Ǘ��ƍ��ʂ̌�������ꏊ�v�i�I���j�ҁw�u�����ʂ̎Љ�w�x��Q���A�O���ЁA�P�X�X�U�N�B�̂��n�ӌ��O�w�i�@�I���ꐫ�̒a���\�s���Љ�ɂ�����̎��ʂƓo�^�x���p�ЁA�Q�O�O�R�N�����j�B
�n�ӌ��O�u�鍑�Ɛl���\�A���n�x�z�̂Ȃ��̐l�ޒm�v�i�I���j�ҁw�u�����ʂ̎Љ�w�x��R���A�O���ЁA�P�X�X�V�N�B�̂��A�O�f�������j�B
�n�ӌ��O�u�w�l���ʖ@�̐V�I���x�|���{�ɂ�����w��@�����̕����v�i�w�����ٍ��ی����x�P�Q�|�R�A�Q�O�O�O�N�R���B�̂��A�O�f�������j�B